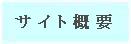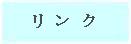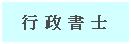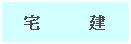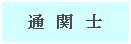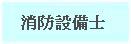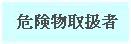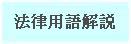相対効
「相対効」とは、相対的に効力を及ぼすことの略で、多数当事者の債権債務関係、特に連帯債務者間での法律行為などで使用されます。相対効とされる場合、一人の債務者のつき生じた事項は他の連帯債務者に効力を及ぼしません。
連帯債務では「相対効の原則」が採用され、相対効とされるものには、以下のものがります。(民法第440条)
- 一人の債務者に生じた時効中断事由のうち、承認、差押え、仮処分
- 時効停止事由(未成年、相続財産、夫婦間、天変・事変)
- 履行遅滞(請求を原因とするもの以外)
「相対効」とされるものは、主に債権者の債権を保護する働きがあります。
相対効以外の効力の働きには以下のものがあります。
- 絶対効
- 負担部分についてのみ絶対効
相対効との違い
絶対効とは、一人の債務者に生じた事項の効力が他の連帯債務者にも及ぶことです。絶対効は一般的に債務者を保護する方向に働きます。
絶対効であるものは以下のものがあります。
- 請求の絶対効(例外的に債権者を保護する働きとなります。民法第434条)
- 相殺を援用した場合の絶対効(民法第436条第1項)
- 免除(民法第437条)
- 混同(民法第438条)
負担部分についてのみ絶対効とは、一人の債務者につき生じた事項の効力は、連帯債務の全額であっても、その一人の負担部分の金額についてのみ、他の連帯債務者に効力が及ぶこととです。
負担部分についてのみ絶対効とされているものは以下のものがあります。
- 相殺を援用しない場合(民法第436条第2項)
- 時効(民法第439条)
したがって、連帯債務の全額につき、一人の債務者が相殺できる債権があったときに、その債務者が援用しない場合は、他の債務者が相殺を援用しない債務者の負担部分のみ援用ができるということになります。
あ い う え お |